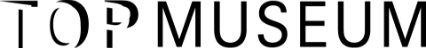News
オサム・ジェームス・中川 <作家インタビュー>
真っ黒な画面の中に
浮かび上がる沖縄のガマ
「イメージの洞窟:意識の源を探る」展にはバックグラウンドの異なるさまざまな作家たちの作品が展示されます。そこで、展示を準備中の出品作家にご登場いただき、作家自身の言葉で作品について、「イメージの洞窟:意識の源を探る」展についてお話しをうかがいました。
オサム・ジェームス・中川さんはニューヨーク市生まれ、東京育ち、そしてアメリカ・ヒューストンでアートと写真を学んだ写真家。現在は、インディアナ大学で教授を務めています。今回、展示する作品は沖縄の洞窟で撮影した〈ガマ〉。いったいどのような作品なのでしょうか。(インタビュー・文=タカザワケンジ)

〈ガマ〉より 2009年 インクジェット・プリント courtesy of PGI 東京都写真美術館蔵
──今回、展示される〈ガマ〉は沖縄の洞窟「ガマ」で撮影されたシリーズです。ガマは地元の人々の祖霊が眠る信仰の場であり、太平洋戦争の沖縄戦で大勢の人が避難し、集団自決に至った痛ましい歴史があります。中川さんの〈ガマ〉はどのように制作されたのでしょうか。
中川■沖縄に初めて行ったのは2001年。きっかけは妻が沖縄出身だったことです。行ってみてそこに僕がよく知っている1970年代のアメリカを発見しました。ただしそれは米軍基地のフェンスの向こうにあるんだけど。そして博物館で沖縄戦のドキュメンタリー・フィルムを見てその悲惨さにショックを受けました。しかもアメリカがやったことだ、と。 〈ガマ〉の前に、〈バンタ〉という作品をつくりました。太平洋戦争で米軍が海上から砲撃した崖を撮影したシリーズです。次に集団自決のことを知り、ガマで撮ろうと思ったのですが、お世話になっていた妻の親戚から大反対されたんです。
──それはなぜでしょうか。
中川■集団自決以前に、ガマは大昔から神聖な場所なんですね。スピリチュアルでパワフルな場所だから、撮影なんてとんでもない。それでも撮りたいと言ったら、ユタのところに行って、僕がガマを撮ってもいいかどうかを聞こうということになりました。ユタというのは沖縄の伝統的なシャーマンで、霊的な相談に乗ってくれる女性です。 ユタに会いに行くと「あなたは沖縄に呼ばれて来ている。ガマに必ず行くでしょう。それを世界中にリリースするでしょう」とあっさり許しがもらえたんですよ。

〈ガマ〉より #023 2011年 インクジェット・プリント courtesy of PGI 東京都写真美術館蔵
──不思議な話ですね。〈ガマ〉は写真集にもなり、世界各地で展示され、文字通りリリースされています。ガマでの撮影はどのようにされたのでしょうか。
中川■アシスタントとガマに入り、三脚にカメラを据え、フォーカスや構図を決めて、カメラのシャッターを開けます。それから露光している間中、僕が懐中電灯を手に壁面を照らしていくのです。真っ暗なガマの中で、肉眼では見えないものに光を当てる。そこにいるかいないかわからないけれど、いるような気がする、亡くなった人たちや、神様に向かってシャッターを開けて「こっちに入っておいで」と呼びかける。それを何度もやって、撮影した写真をパソコン上でつなげて超高解像度の1枚の写真にします。見えないものを見ようとする努力の結果なんです。
──露光時間が長いため写ってはいませんが、中川さん自身が動いて光を当てているんですね。実はすべての写真の中に中川さんがいる。〈ガマ〉には高解像度の作品のほかに、一見、真っ黒に見える作品〈闇〉もありますね。こちらはどのようにつくられたのですか。
中川■解像度が高くハイパーリアルな〈ガマ〉を、日本やアメリカで展示してみて、オーディエンスが見ているものと、僕が実際にガマの中にいた経験とちょっとズレがあるんじゃないかと感じるようになりました。
そんな時、ヒューストンでリチャード・セラの展覧会があって、彼のドローイング作品を見たんですよ。真っ黒の、とてつもなく大きい作品でした。それを見て、インスピレーションを受けたんです。真っ黒なんだけど、時間が経って目が慣れてくるとだんだん何かが見えてくる。これが洞窟にいる時の感覚だ、と思いました。
それからリチャード・セラをリサーチしたんですけど、すごくいいことを言っている。「ドローイングはいつもペインティングの下に隠れてる。僕はその隠れたドローイングを見せたい」。この言葉もヒントになりました。

〈闇〉より #036 2015年 インクジェット・プリント
中川■〈闇〉は、アワガミファクトリー(阿波和紙の企業組合)の楮二層紙(コウゾウニソウシ:インクジェット対応和紙の一種)にガマの写真をプリントし、その上に墨を吹き付けたり、紙の裏に墨を塗ったものです。
ハイパーリアルな〈ガマ〉では、紙にプリントしているのに本物の岩肌のように見えました。触ろうとしたオーディエンスがいたくらい。つまりこれは紙じゃないみたいだと思わせた。だったら逆に、今度は紙だってことを意識させよう。そこでアワガミを使うことにしました。
アワガミに出合ったのは、東京藝術大学でワークショップをやった時でした。学生たちとアワガミに写真をプリントしたんです。アワガミは濡らしてもインクが落ちず、水に強い。濡らしちゃおう、珈琲につけようって遊んでみました。たまたまその中に日本画専攻の学生がいて、いろいろな種類の墨を持ってきてくれた。水で濡らしたアワガミに墨を塗ると真っ黒になる。でもドライヤーで乾かすと下にあるイメージが浮かび上がってくる。これって暗室での作業に似ているなあ、と思ったんです。
〈闇〉は東京藝術大学大学美術館陳列館の「《写真》見えるもの/見えないもの #02」展(2015)で展示しました。今回はその時にできなかったことをやります。イメージがあるほうだけでなく、裏面もお見せします。学芸員の丹羽さんの提案でプリントを吊すことにしたんです。僕にとっても初めての試みです。先日、展示の実験で初めて吊してみたんですが、後ろを見て、前を見て、という見方ができるのはすごく面白かった。裏から光を当ててみたら、意外なディテールが見えてきたりもしました。
──真っ黒に見えますけど、実はその下には洞窟のイメージがあるんですね。じーっと見ているとゆっくりと見えてくる。
中川■写真って、パッと見て、ぜんぶ見えると思っていますよね?見て、わかった気がしちゃってるんじゃないですか。写真が危険なのはそこです。わからないものはダメだと思い込んでる。でも、抽象画を見る時に「わからないからダメ」とは思わないでしょう。わからないまま見ているうちにいろんなものに見えてくる。それが楽しい。そう考えると、何かが見えてくる、「appear(現れる)」っていう経験をすることが、写真にはあまりないんですね。
でも、実は写真家は暗室でappearを経験しているんですよ。現像液の中の印画紙にイメージが浮かんでくるという瞬間を見て感動している。でも、できあがった写真を見る人たちはそれを見ることができない。墨が乾いてきた時にイメージがじわっと見えてきて、暗室だ!と思ったというのはこのことなんです。 暗室の中で写真家が見ていることを、作品として見せている人は誰もいないんじゃないかな。僕がやっているのはたぶんそれに近いことだと思います。それもデジタルでね。
──最後にこの展覧会のテーマについてうかがいたいのですが、中川さんにとって洞窟とはどんなものでしょうか。
中川■洞窟は大昔から人間と深い関わりがありますよね。キリスト教もイスラム教も、仏教も神道も、みんな洞窟を聖地にしています。なぜかと考えると、明るいところから真っ暗闇に入って、何も見えなくなる。そういう状況の中で、頭の中でイメージを描くことを練習してきたからじゃないでしょうか。
僕自身、ガマに入ったことで、アーティストとして変わったのかもしれない。洞窟には光がないのに、そこで写真をつくろうと思うことが写真の原理に反しているし、アワガミにプリントしてその上に墨を塗ったのも、いままでも僕だったら思いつかなかったかもしれない。
〈闇〉は、黒の中に浮かび上がってくるものが見ている人によってそれぞれ違うと思います。見て、わかった、終わり、じゃない。自分だけのイメージが見つかると思います。写真は見てパッとわかるもんじゃない。写真はこういうものだ、という思い込みを裏切るような作品になったと思います。
(2019年7月)
「イメージの洞窟:意識の源を探る」展 詳細はこちら
浮かび上がる沖縄のガマ
「イメージの洞窟:意識の源を探る」展にはバックグラウンドの異なるさまざまな作家たちの作品が展示されます。そこで、展示を準備中の出品作家にご登場いただき、作家自身の言葉で作品について、「イメージの洞窟:意識の源を探る」展についてお話しをうかがいました。
オサム・ジェームス・中川さんはニューヨーク市生まれ、東京育ち、そしてアメリカ・ヒューストンでアートと写真を学んだ写真家。現在は、インディアナ大学で教授を務めています。今回、展示する作品は沖縄の洞窟で撮影した〈ガマ〉。いったいどのような作品なのでしょうか。(インタビュー・文=タカザワケンジ)

〈ガマ〉より 2009年 インクジェット・プリント courtesy of PGI 東京都写真美術館蔵
──今回、展示される〈ガマ〉は沖縄の洞窟「ガマ」で撮影されたシリーズです。ガマは地元の人々の祖霊が眠る信仰の場であり、太平洋戦争の沖縄戦で大勢の人が避難し、集団自決に至った痛ましい歴史があります。中川さんの〈ガマ〉はどのように制作されたのでしょうか。
中川■沖縄に初めて行ったのは2001年。きっかけは妻が沖縄出身だったことです。行ってみてそこに僕がよく知っている1970年代のアメリカを発見しました。ただしそれは米軍基地のフェンスの向こうにあるんだけど。そして博物館で沖縄戦のドキュメンタリー・フィルムを見てその悲惨さにショックを受けました。しかもアメリカがやったことだ、と。 〈ガマ〉の前に、〈バンタ〉という作品をつくりました。太平洋戦争で米軍が海上から砲撃した崖を撮影したシリーズです。次に集団自決のことを知り、ガマで撮ろうと思ったのですが、お世話になっていた妻の親戚から大反対されたんです。
──それはなぜでしょうか。
中川■集団自決以前に、ガマは大昔から神聖な場所なんですね。スピリチュアルでパワフルな場所だから、撮影なんてとんでもない。それでも撮りたいと言ったら、ユタのところに行って、僕がガマを撮ってもいいかどうかを聞こうということになりました。ユタというのは沖縄の伝統的なシャーマンで、霊的な相談に乗ってくれる女性です。 ユタに会いに行くと「あなたは沖縄に呼ばれて来ている。ガマに必ず行くでしょう。それを世界中にリリースするでしょう」とあっさり許しがもらえたんですよ。

〈ガマ〉より #023 2011年 インクジェット・プリント courtesy of PGI 東京都写真美術館蔵
──不思議な話ですね。〈ガマ〉は写真集にもなり、世界各地で展示され、文字通りリリースされています。ガマでの撮影はどのようにされたのでしょうか。
中川■アシスタントとガマに入り、三脚にカメラを据え、フォーカスや構図を決めて、カメラのシャッターを開けます。それから露光している間中、僕が懐中電灯を手に壁面を照らしていくのです。真っ暗なガマの中で、肉眼では見えないものに光を当てる。そこにいるかいないかわからないけれど、いるような気がする、亡くなった人たちや、神様に向かってシャッターを開けて「こっちに入っておいで」と呼びかける。それを何度もやって、撮影した写真をパソコン上でつなげて超高解像度の1枚の写真にします。見えないものを見ようとする努力の結果なんです。
──露光時間が長いため写ってはいませんが、中川さん自身が動いて光を当てているんですね。実はすべての写真の中に中川さんがいる。〈ガマ〉には高解像度の作品のほかに、一見、真っ黒に見える作品〈闇〉もありますね。こちらはどのようにつくられたのですか。
中川■解像度が高くハイパーリアルな〈ガマ〉を、日本やアメリカで展示してみて、オーディエンスが見ているものと、僕が実際にガマの中にいた経験とちょっとズレがあるんじゃないかと感じるようになりました。
そんな時、ヒューストンでリチャード・セラの展覧会があって、彼のドローイング作品を見たんですよ。真っ黒の、とてつもなく大きい作品でした。それを見て、インスピレーションを受けたんです。真っ黒なんだけど、時間が経って目が慣れてくるとだんだん何かが見えてくる。これが洞窟にいる時の感覚だ、と思いました。
それからリチャード・セラをリサーチしたんですけど、すごくいいことを言っている。「ドローイングはいつもペインティングの下に隠れてる。僕はその隠れたドローイングを見せたい」。この言葉もヒントになりました。

〈闇〉より #036 2015年 インクジェット・プリント
中川■〈闇〉は、アワガミファクトリー(阿波和紙の企業組合)の楮二層紙(コウゾウニソウシ:インクジェット対応和紙の一種)にガマの写真をプリントし、その上に墨を吹き付けたり、紙の裏に墨を塗ったものです。
ハイパーリアルな〈ガマ〉では、紙にプリントしているのに本物の岩肌のように見えました。触ろうとしたオーディエンスがいたくらい。つまりこれは紙じゃないみたいだと思わせた。だったら逆に、今度は紙だってことを意識させよう。そこでアワガミを使うことにしました。
アワガミに出合ったのは、東京藝術大学でワークショップをやった時でした。学生たちとアワガミに写真をプリントしたんです。アワガミは濡らしてもインクが落ちず、水に強い。濡らしちゃおう、珈琲につけようって遊んでみました。たまたまその中に日本画専攻の学生がいて、いろいろな種類の墨を持ってきてくれた。水で濡らしたアワガミに墨を塗ると真っ黒になる。でもドライヤーで乾かすと下にあるイメージが浮かび上がってくる。これって暗室での作業に似ているなあ、と思ったんです。
〈闇〉は東京藝術大学大学美術館陳列館の「《写真》見えるもの/見えないもの #02」展(2015)で展示しました。今回はその時にできなかったことをやります。イメージがあるほうだけでなく、裏面もお見せします。学芸員の丹羽さんの提案でプリントを吊すことにしたんです。僕にとっても初めての試みです。先日、展示の実験で初めて吊してみたんですが、後ろを見て、前を見て、という見方ができるのはすごく面白かった。裏から光を当ててみたら、意外なディテールが見えてきたりもしました。
──真っ黒に見えますけど、実はその下には洞窟のイメージがあるんですね。じーっと見ているとゆっくりと見えてくる。
中川■写真って、パッと見て、ぜんぶ見えると思っていますよね?見て、わかった気がしちゃってるんじゃないですか。写真が危険なのはそこです。わからないものはダメだと思い込んでる。でも、抽象画を見る時に「わからないからダメ」とは思わないでしょう。わからないまま見ているうちにいろんなものに見えてくる。それが楽しい。そう考えると、何かが見えてくる、「appear(現れる)」っていう経験をすることが、写真にはあまりないんですね。
でも、実は写真家は暗室でappearを経験しているんですよ。現像液の中の印画紙にイメージが浮かんでくるという瞬間を見て感動している。でも、できあがった写真を見る人たちはそれを見ることができない。墨が乾いてきた時にイメージがじわっと見えてきて、暗室だ!と思ったというのはこのことなんです。 暗室の中で写真家が見ていることを、作品として見せている人は誰もいないんじゃないかな。僕がやっているのはたぶんそれに近いことだと思います。それもデジタルでね。
──最後にこの展覧会のテーマについてうかがいたいのですが、中川さんにとって洞窟とはどんなものでしょうか。
中川■洞窟は大昔から人間と深い関わりがありますよね。キリスト教もイスラム教も、仏教も神道も、みんな洞窟を聖地にしています。なぜかと考えると、明るいところから真っ暗闇に入って、何も見えなくなる。そういう状況の中で、頭の中でイメージを描くことを練習してきたからじゃないでしょうか。
僕自身、ガマに入ったことで、アーティストとして変わったのかもしれない。洞窟には光がないのに、そこで写真をつくろうと思うことが写真の原理に反しているし、アワガミにプリントしてその上に墨を塗ったのも、いままでも僕だったら思いつかなかったかもしれない。
〈闇〉は、黒の中に浮かび上がってくるものが見ている人によってそれぞれ違うと思います。見て、わかった、終わり、じゃない。自分だけのイメージが見つかると思います。写真は見てパッとわかるもんじゃない。写真はこういうものだ、という思い込みを裏切るような作品になったと思います。
(2019年7月)
「イメージの洞窟:意識の源を探る」展 詳細はこちら