恵比寿映像祭2023
コミッション・プロジェクト
2023.2.21(火)—3.26(日)
- 開催期間:2023年2月21日(火)~3月26日(日)
- 休館日:毎週月曜日(月曜日が祝休日の場合は開館し、翌平日休館)
- 料金:入場無料 ※「TOPデジタルスタンプラリー2022-2023」対象
本展はオンラインによる日時指定予約を推奨いたします。![]()
>日時指定予約Webketページ(外部サイト)
恵比寿映像祭2023は、日本を拠点に活動する新進作家4名を選出し、制作委嘱した映像作品を「新たな恵比寿映像祭」の成果として発表する「コミッション・プロジェクト」を開始します。映像表現に通じた国内外の有識者5名が審査委員により選出された作家は、東京都写真美術館の3F展示室で新作の未発表作品を発表。また、会期中に4作品のなかから特別賞を決定します。
恵比寿映像祭2023 コミッション・プロジェクト
選出アーティスト|
荒木 悠|ARAKI Yu
ワシントン大学で彫刻を、東京藝術大学では映像を学ぶ。日英の通訳業を挫折後、誤訳に着目した制作を始める。英語圏において、「鋳造」と「配役」がどちらも「キャスティング(casting)」と呼ばれていることを起点に、オリジナルからコピーが作られる過程で生じる差異を再現・再演・再生といった表現手法で探究している。2018年はアムステルダムのライクスアカデミーにゲスト・レジデントとして滞在。2019年フューチャージェネレーション・アートプライズのファイナリストに選出。2020-21年度アーツコミッション・ヨコハマU39アーティストフェロー。
葉山 嶺|HAYAMA Rei
野生動物や環境問題と深く関わる特殊な環境で幼少期を過ごす。多摩美術大学造形表現学部映像演劇学科で学び、2008年より映像制作を始める。自然と人間との調和を求める彼女の作品は、人間中心的な視点から失われたり、無視されたりする自然や生き物を中心に展開され、人間には見ることができない「自然の現実の層」を人間の想像力の中に浮かび上がらせる。近年では、BonnerKunstverein(ドイツ)、NationalGalleryofZimbabwe(ジンバブエ)、JeudePaume(フランス)、SifangArtMuseum(中国)、釜山ビエンナーレ2020、NTTインターコミュニケーション・センター[ICC](東京)、EmptyGallery(香港)などで展示・上映されている。
金 仁淑|KIM Insook
韓国の漢城大学芸術大学院西洋画科写真映像コースに留学後、15年間のソウル暮らしを経てソウルと東京を拠点に制作活動を展開。「多様であることは普遍である」という考えを根幹に置き、「個」の日常や記憶、歴史、伝統、コミュニティ、家族などをテーマに制作を行い、写真・映像を主なメディアとして使用したインスタレーションを発表している。2008年に光州市立美術館で個展「sweethours」を開催。韓国国立現代美術館や、ドイツ・デュッセルドルフ市などが運営するアーティスト・イン・レジデンシーで滞在制作を行い、大邱フォトビエンナーレ、森美術館(東京)、東京都写真美術館など、国内外の芸術祭や企画展で作品を発表する。
大木裕之|OKI Hiroyuki
東京生まれ。高知県、東京都、他各地拠点。東京大学工学部建築学科在学中の80年代前半より映像制作を始める。1990年にイメージフォーラム・フェスティバル審査員特別賞を受賞、1996年第46回ベルリン国際映画祭ネットパック賞を受賞。その表現活動は映像に留まらず、ドローイング、インスタレーション、パフォーマンスにまでおよぶ。世界各地を移動しながら生活と哲学の相関関係を探り、動的ネットワークで複雑に構成される世界を描き出す。独特で詩的な映像表現は国内外で高く評価され、国際展および映像祭に多数参加。
審査委員|
沖 啓介(メディア・アーティスト、東京造形大学特任教授)
斉藤綾子(映画研究者、明治学院大学教授)
レオナルド・バルトロメウス(山口情報芸術センター[YCAM]キュレーター)
メー・アーダードン・インカワニット(映画・メディア研究者、キュレーター、ウェストミンスター大学教授)
田坂博子(東京都写真美術館学芸員、恵比寿映像祭キュレーター)
審査運営事務局:特定非営利活動法人アーツイニシアティヴトウキョウ [AIT/エイト]
共催:サッポロ不動産開発株式会社
後援:J-WAVE 81.3FM
協賛:東京都写真美術館支援会員
※事業は諸般の事情により変更することがございます。 あらかじめご了承ください。
関連イベント
- アーティスト・トーク:荒木悠
- 2023年3月19日(日) 10:30~12:30 終了致しました
出品作家とゲストによるアーティスト・トークを開催します。
トーク登壇|荒木悠(出品作家)、WISS(ジーン福嶋、ピーター関、ポール宅間、エース広瀬、エリック波部)
会場|東京都写真美術館1階ホール
定員|190名
参加費|無料
参加方法|10:00より1階総合受付にて整理券を配布。※予告なく出演者に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。 - アーティスト・トーク:金仁淑
- 2023年3月19日(日) 18:00~20:00 終了致しました
出品作家とゲストによるアーティスト・トークを開催します。
トーク登壇|金仁淑(キム・インスク/出品作家)、山田創(滋賀県立美術館学芸員)
会場|東京都写真美術館1階ホール
定員|190名
参加費|無料
参加方法|10:00より1階総合受付にて整理券を配布。 - アーティスト・トーク+上映(大木裕之)
- 2023年3月25日(土) 17:00~18:00 上映 終了致しました
2023年3月25日(土) 18:00~20:00 アーティスト・トーク 終了致しました
出品作家とゲストによるアーティスト・トークと作品上映を開催します。
上映作品
《ウム/オム1》(2005-2010年)
《松前君の赤い (パブリックパンツ) 映画 (恵比寿ヴァージョン) 》(2010-2011年)
トーク登壇|大木裕之(出品作家)、伊藤亜紗(東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授)
会場|東京都写真美術館1階ホール
定員|190名
参加費|無料
参加方法|10:00より1階総合受付にて整理券を配布。 - アーティスト・トーク+上映:葉山嶺
- 2023年3月26日(日) 17:00~18:30 上映 終了致しました
2023年3月26日(日) 18:30(上映終了後)~20:00 アーティスト・トーク 終了致しました
出品作家とゲストによるアーティスト・トークと作品上映を開催します。
上映作品
《TheirBird》(2010-2012年) 13分08秒
《Emblem》(2012年) 15分38秒
《Reportage!》(2015年) 1分20秒
《SomeSmallnessComingFromLand》(2015年) 24分56秒
《OnTheCollinearAndReflectedOnTheWater》(2018年) 3分42秒
《ThePearlOfTailorbird》(2019年) 28分47秒
トーク登壇|葉山嶺(出品作家)、清水知子(東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科准教授)
会場|東京都写真美術館1階ホール
定員|190名
参加費|無料
参加方法|10:00より1階総合受付にて整理券を配布。
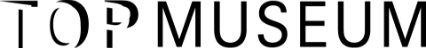

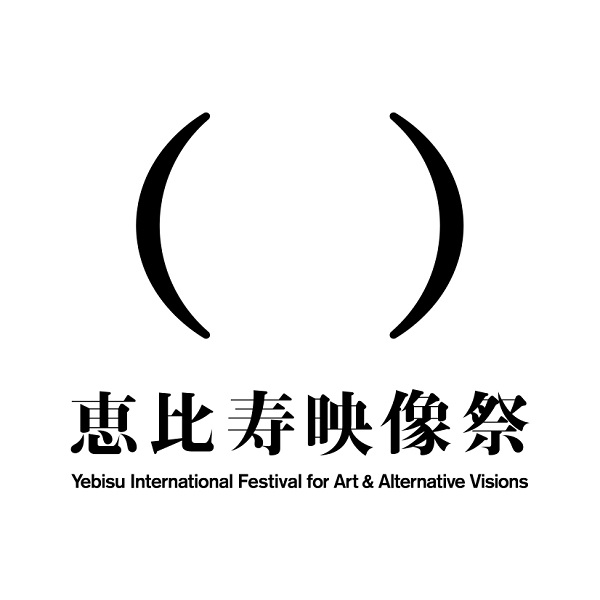
![出品作品リスト1[pdf]](http://topmuseum.jp/upload/3/4268/thums/YEBIZO2023_booklist_COMMISSION PROJECT_02.png)