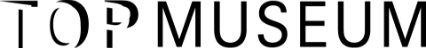作者インタビュー
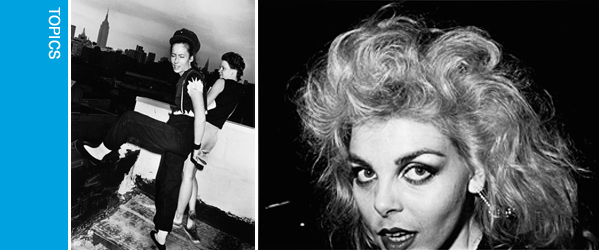
ニューヨーク イースト・ヴィレッジ/NEW YORK East Village 1981
ニューヨーク ブロードウェイ/NEW YORK Broadway 1985
-北島敬三が70~80年代に撮影したストリートスナップを中心に構成される東京都写真美術館の「北島 敬三 1975-1991」展。数十年前の写真を今見せることの意味とは?
6年くらい前から手元に残っているネガを全部見直して、あらためてプリントを作っているのですが、それは私にとって単に「昔の写真」ではありません。それを現在に接続する回路というものがどこかに残されているはずですし、何でもない一枚の写真がある時突然リアリティをもって立ち上がってくる可能性は常に存在し続けているのではないでしょうか。そういう写真の物質的抵抗力に賭けてみたくて、今回は初期のストリートスナップを中心に構成することにしました。
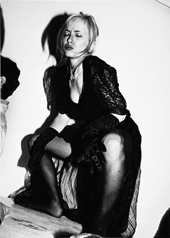
ニューヨーク クラブ スタジオ54/NEW YORK Club STUDIO 54 1982
-「WORKSHOP写真学校」の森山大道教室から、自主運営ギャラリー「CAMP」へ。森山をして「白昼の通り魔」と言わしめた若きイメージハンターは「CAMP」のシンボルマークであった蝿のように都市の雑踏を自在に飛び回り、行き交う人々の姿をカメラに収めていった。森山大道の圧倒的な影響下で写真を始めながらも、独自の道を摸索する北島が出会った最初の被写体は、ベトナム戦争下に栄えた沖縄の歓楽街、コザ(現沖縄市)であった。
1975年にとりあえず入っただけの大学を辞めて「WORKSHOP写真学校」へ行きました。その後は森山さんたちと立ち上げた自主ギャラリー「CAMP」を拠点にしばらく活動していましたが、当時森山さんに「人間を撮らなきゃだめだよ」といわれたことをよく覚えています。まだ写真を始めたばかりの私は「人を撮る」という森山さんの欲望を半ば引き受けるような形で撮影に向かった部分があったのかもしれません。
最初に「復帰」後間もない沖縄と東京を往復しながら、その後はニューヨーク、西ベルリン、東ヨーロッパなどに滞在して手探りで撮っていきました。結果的に冷戦期の西と東を象徴する場所を選んでいることになるわけですが、やはり被写体として面白い場所はそういう政治的緊張感のある都市だったのでしょう。ただ最初に撮ったコザに関しては、「沖縄」という問題が自分の中で大きくなってきたこともあり、発表しきれずに挫折してしまいました。若かったからかもしれませんが、今度撮る時はどんなにつらくても発表しようと、逆にいえばそう思えない場所は撮らないと決めました。コザをきっかけにして行ったニューヨークは、資本主義陣営を代表する街だけあって、広告やテレビなどのイメージに浸透されつくしたかのような人々の姿が印象的で、その後に撮影した東ヨーロッパとは人の顔も全然違いました。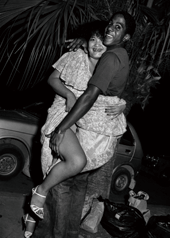
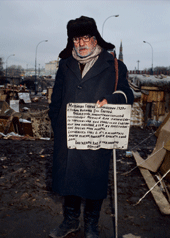
コザ ビジネスセンター/KOZA BUSINESS CENTER 1979
モスクワ ロシア共和国/MOSCOW ROSSIA 1991
-1991年、崩壊直前のソ連を撮影した北島は、その16年後になって「U.S.S.R.1991」を発表。忘却の淵から這い出してきたかのような旧ソ連の人々の姿はわれわれを驚かせた。歴史に対する「写真の物質的抵抗力」をまざまざと見せつけられた形となったが、ファインダー越しの瞬間だけでなく、それを見せる時をもとらえることに長けた写真家だといえる。冷戦構造の終わりとともに都市の様相が劇的に変化していった90年代、ストリートスナップの名手がその強力な武器であった小型カメラの機動力を捨てて、大型カメラによる肖像のアーカイヴへと向かう。
15年くらいスナップショットを続けましたが、シャッターチャンスや、フレーミングに重きを置くような写真がだんだんとつまらなく思えてきて、3、4年モヤモヤした状況が続いた中で、1991年に雑誌の仕事を兼ねてソ連へ撮影に行きました。ソ連という一つの体制が崩壊することによって、そこに住む人の顔も服装も一変してしまうことを目の当たりにしたこともあり、顔が自分の主題として大きくなっていきました。この時期の撮り方としてはストリートスナップとポートレイトの中間で、その人が身につけている社会的地位を示すような記号や、属している空間も含めた全身像を撮っていました。ちょうど試行錯誤していた時期のものです。街を歩きながら撮影する方法にリアリティを感じられなくなったこともあり、90年代あたりから三脚と大型カメラで複数の人物の肖像を経年的に撮っていく方法に切り替えて、それが現在まで続く「PORTRAITS」のシリーズになっています。
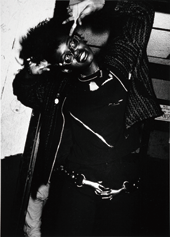
プラハ/PRAGUE 1983
ニューヨーク イースト・ヴィレッジ/NEW YORK East Village 1981
-肖像から表情や背景を削ぎ落とし、最後に残った「ただの顔」の集積とそこから見えてきたものとは。時とともに変容する写真群。
「PORTRAITS」は白いシャツを着た人を白バックで証明写真のように撮影していく作業なので、シャッターチャンスや「いい写真」「悪い写真」ということも起こりえないはずです。そうすると全ての写真が等価で、極端にいえば「古い写真」や「新しい写真」も関係なくなって、構造的には一枚一枚が横並びの写真群になります。そういう作業を継続していくうちに、だんだんと昔撮った写真も現在の「PORTRAITS」と同じ手つきで扱うべきなのではないかと考えるようになりました。
写真を単なる過去の記録として消費するのではなくて、それを「現在の写真」として甦らせるような回路を開いてやることが重要なのではないでしょうか。撮影から何十年と時間が経つと、かつて撮った場所も政治的状況の変化と共に大きく姿を変えており、もう写真の中にしか存在していませんが、その写真は「現在の写真」としてまざまざと存在しています。言葉やほかのメディアとは違った写真のモノとしての抵抗力を、この展覧会で私自身も見てみたいのです。だから「私の写真」というよりも、写真を介してそこに写っている人やその場所を見てもらいたいし、今の自分は丁寧にプリントを仕上げることなのだと思います。
(インタビュー 2009年4月)
__________________________________________________
インタビューと文 小原真史(kohara masashi)
映像作家。監督作品に『カメラになった男 写真家 中平卓馬』。現在、古屋誠一のドキュメンタリー映画を撮影中。 IZU PHOTO MUSEUM研究員。